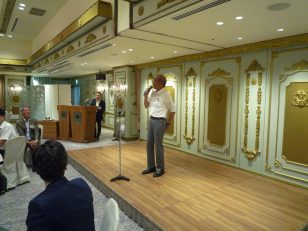【講演会】
講 師:公認会計士・税理士 山田 毅志 様
(税理士法人タクトコンサルティング/代表社員)
(株式会社タクトコンサルティング/代表取締役社長)
演 題:普通とは違う「最近の事例」のご紹介
[講演概要]
・税理士法人タクトコンサルティングは、創業より50周年を迎え、現在法人顧問の業務は行っておらず、株価承継や不動産対策の業務を中心にしている。
・国の一般会計歳入総額は凡そ115兆円で、消費税25兆円、所得税23兆円、法人税19兆円である。
・相続税は令和5年度で3兆円であり、被相続人は157万人、内申告書を提出しているのは15万5千人で約10%である。税額は3兆円と大きくはないが、話題になることが多い。
[1] 最近のトレンド
・「最近のトレンド」として、特に資産税の分野で相続税評価がポイントになってきている。とりわけ①不動産②未公開株式において「時価」が問題となる。
・「相続税評価」は、「財産評価基本通達」に規定/運用されている。評価の原則は、1(2).財産の価額は、時価によるものとし、①時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいい(取引時価)、②その価額は、この通達の定めによって評価した価額による(通達評価≒相続税評価額)。6.この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する(総則6項)。
[2]最近の弊社(私)の案件のご紹介
(1)総則6項事案「令和4年4月19日最高裁判所判決」
①被相続人(91歳)は、相続3年前に不動産を2件13億8700万円で購入した。その時の借入金額は9億6000万円であった。②その後相続が発生し、その不動産の当初申告額は3億3000万円(通達評価による)であったが、時価(不動産鑑定金額)は8億円であった。③購入資金の借入先銀行の「貸出稟議書」に、相続税対策を目的として不動産購入を計画、購入資金につき借入れの依頼があった旨明記されている。
⇒税務署は、国税庁通達の評価額(相続税評価額)でなく、不動産鑑定評価額による相続税に更生処分した。
⇒(R4/4/19判決)①申告額と時価に「著しい乖離」があり、②「通達をそのまま適用せずに他の評価方法によることが合理的と考えられる事情が存在」する場合には総則6項の適用を認めるという指針を示した。
⇒以降総則6項発動が国税局で増加している。
・弊社でも、R4/4/19判決を踏まえて適切に対応した案件を有する。
(2)相続人のいない相続事案
・相続人数が0の案件は、令和5年808件であった。
・法定相続人になる者がおらず、かつ遺言書を用意していなかったため、相続財産を取得する者がいない状態で、所定の手続きを経て最終的に国庫に帰属する。
・資産家ほど、その傾向が強いように思える。
(3)争う相続(争族)
・遺言を残していた場合の遺留分侵害額請求において、従来は遺留分減殺請求権という物権的請求権とされていたが、令和元年7月以降は金銭的請求権とされ、取り戻すことができるのは、金銭でということになった。
・争族になった場合の土台(争いのテーブル)は税法ではなく民法である点に留意が必要である(「相続税評価額」ではなく、「取引時価」での争いになる)。
以上
HOTEL PLUMM(横浜市西区北幸2-9-1)にて、役員会・講演会・懇親会を開催しました。
演会後の懇親会では斉藤昌喜会長よりご挨拶、加藤健平副会長の乾杯の音頭でスタートし、
その後、多くの会員の方々からのご挨拶やトークが続きました。最後は山田智也副会長の音頭に
よる締めで本例会は終了しました。